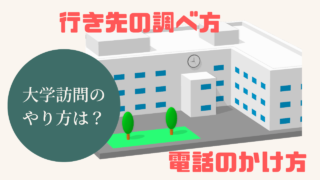大学訪問の目的を、学内合同説明会(以下学内合説)の参加にしている会社もあることでしょう。
今回は学内合説への参加方法や、その実情をお伝えしていきたいと思います。
学内合説の主催者と運営
多くの大学において、学内合説は基本的にキャリアセンターが主催しています。
一部、キャリアセンターではなく学生の有志が行っている大学もありましたが、これは稀なケースなので、「学内合同説明会はキャリアセンターが主催している」と捉えて頂いて問題ないです。
ただし、あくまで主催であり、「運営」や「申し込み」に関してはキャリアセンターが行っていないケースも多く存在します。
まず学内合説の運営に関してですが、こちらは年々キャリアセンターが独自に運営するよりも、キャリタスや学情、ユニバースクリエイトなどといった会社に、運営を委託するケースが増えている印象を受けます。
(大学によっては開催日程毎に委託していますケースもあります)
企業側への案内連絡、学生側への広報活動、双方への運営に関する連絡や、当日の運営などやることが非常に煩雑な学内合説ですが、面倒なことを任せることが出来る大学側と、大学とのパイプ構築や学生への自社媒体等の広報が出来る委託される会社が側の思惑が、絶妙に合致するあたりが最近増加している原因でしょうか?
一方で企業の選定や誘致、各社への連絡、学生への広報、当日の運営など全てをキャリアセンターが行っている大学や、準備段階までを委託し、当日の運営は大学が行うケースなども見受けられます。

学内合説の参加方法
学内合説に参加する方法としては、大きく次の3つのパターンに分けることができます(個人的な区分けですが)。
大学のホームページで応募受付
大学によって時期は様々ですが、早いところでは7月末くらいからHP上で受付が開始され、1カ月程度募集を行っています。
締め切り後に応募が総数を上回った場合は抽選(大学側が選定)になり、当選した企業に改めて学内合説の案内(時間や実施形式など詳細)が届きます。多くの場合は、ここで申し込みをすることで正式な申込みとなります(キャンセル料が発生するタイミング)。
落選した企業には、「ごめんなさいメール」が同時に届きます。
誤って落選した企業宛に、当選した企業への詳細メールを送ってしまうことも以前あり笑った記憶があります。
大学側が選定
企業からの一般公募を行わず、大学側が来てほしい企業を選定して声をかけるパターンです。
参加希望の連絡をした時や、キャリアセンターを訪問した際に、参加希望を聞いてくれる大学も多いですが、このパターンを取っている多くの大学の場合は、基本的にこの「希望を聞く」という行為自体が形式的なものであり、新規で参加できる可能性は低いです。
希望用紙のような物がなく、口頭で申し込み希望を聞いてくれる大学は、ほぼ100%に近い確率でリップサービスです(笑)
サイト上で受付
「キャリタスCMS」や「ツナガク」から登録アドレスに案内が届き、そこから申込を行うパターンです。
こちらはわざわざHP等をチェックしなくて良いので非常に便利です。
ちなみにキャリタスCMSは大学ごとに管理画面が異なり(別サイトのようなもの)ますので申込の際はご注意下さい。
応募が多かった場合の選定方法に関しては、(これまでいくつかの聞いた話からすると)委託会社で行っているケースと、大学側が応募してきた企業名を確認して選定するケースがあるようです。
参加実績企業
前年に参加実績のある企業の場合、HP掲載よりも前(同時も場合も有)に、別でメールが来たり、申し込みの詳細が郵送されてくるケースもあります。※ファンクラブの選考申込に似てます。
ただし全ての大学がこのパターンではないので、「昨年参加したから今年も大丈夫」と待っているだけではなく、一度問い合わせした方がよいでしょう。
中には単純に「申し込み順」という選定を行っている大学もありますので早めに対応しましょう。
学内合説の申込時期と開催時期と開催方法
学内合同説明会の運営や参加方法についてご理解頂けたところで、ここからは「申込みの時期」・「開催する時期」「開催方法」について解説していきます。
まず学内合説の申込時期ですが、こちらは前述したように「7月~11月」くらいの期間で行う大学が多く、抽選などの結果報告がそれぞれの時期の「1ヶ月~1ヶ月半後」になり、そこから本申込という流れになることが多いです。
次に学内合説が開催される時期ですが、こちらは「3月上旬の2週間」で行う大学が多く、一斉に企業を集めて大きく1日で開催するもの、数日間にかけて開催するもの、1週間~2週間の期間を設けて細かく開催するものと、大学によって様々です。
また合説当日の開催時間に関してですが、多くの大学で「午前午後で企業を入れ替えをするパターン」、「午後だけで開催するパターン」この二つが多い印象を受けます。(1日使って実施するケースも稀に見かけますが)
最後に開催方法ですがこちらは大きく2パターンです。
1つはタイムテーブルが決まっており、参加企業にはその時間内で説明をしてもらい、学生の移動を施す形式のもの。2つ目は、開催時間全体の中で学生が自由に企業を回る形式のものです。
どちらにせよ、学生の動きはリクナビやマイナビなどナビ会社が開催する合説と同じなので、あまり違和感はないでしょう(開場前の講演やパネルディスカッションなどがない程度)。
学内合説で優先される会社
ここまで読んで頂き、概要は理解したものの、これから学内合説に申し込みを行う企業にとっては「新規で参入できるか?」という疑問がうまれると思います。
こちらは結論から言ってしまうと「難しいですが企業や業種による」となります。
もう少し詳しく言えば、大企業や有名企業(人気企業)・人気業種は参加できる可能性はあります。
大学の就職支援という観点から言えば、重要なのは「高い内定率」と「有名企業への内定」です。この数字と企業名は学生募集に大きく関わる要素になるので、出来るだけそういった企業と繋がっておきたい思惑が大学にはあります。
またキャリアセンター・委託会社問わず、当日学生を集客することは大きなミッションの一つになるので、学生が集まりやすい人気企業や、大企業に参加してもらうことは重要になってくるのです。
逆に業種などによっては、企業規模が大きかったとしても相手にしてもらえないケースがあります。
(事業内容や企業内部の良し悪しというよりも、あくまで世間的な印象というケースが多いです)

ちなみに、地方大学などは地元企業を優先する傾向があります(地域活性化の意味合いもあるので良い試みだと思います)。
学内合説に新規で参加する方法
学内合説に新規で参加する方法、それは「コネを使うこと」です。
キャリアセンター職員の方の中には、自身の枠を持っているような人もいるので、親しくなっていくとその枠を譲ってくれる場合もあります。
また、お知り合いの先生がいる場合などは聞いてみてもいいのではないでしょうか?
たまたまその先生がキャリアセンターに影響力のある方の場合、何年もかけて落選し続けていたものがすんなり参加出来たような例もあります。
参加のしやすさで言うと、地方大学の方が参入しやすいような気もします(あくまで個人的な経験や印象)。
しかしここまで挙げた事例を用いても、業種や職種で参加企業を決めているような大学もあるので、そういった大学の場合は方針が変わらない限りは参加が難しいです。
学内合説への参加ですが、「継続して依頼すること」「タイミング」「担当者」。この3つの要素が重要になってくると思います。