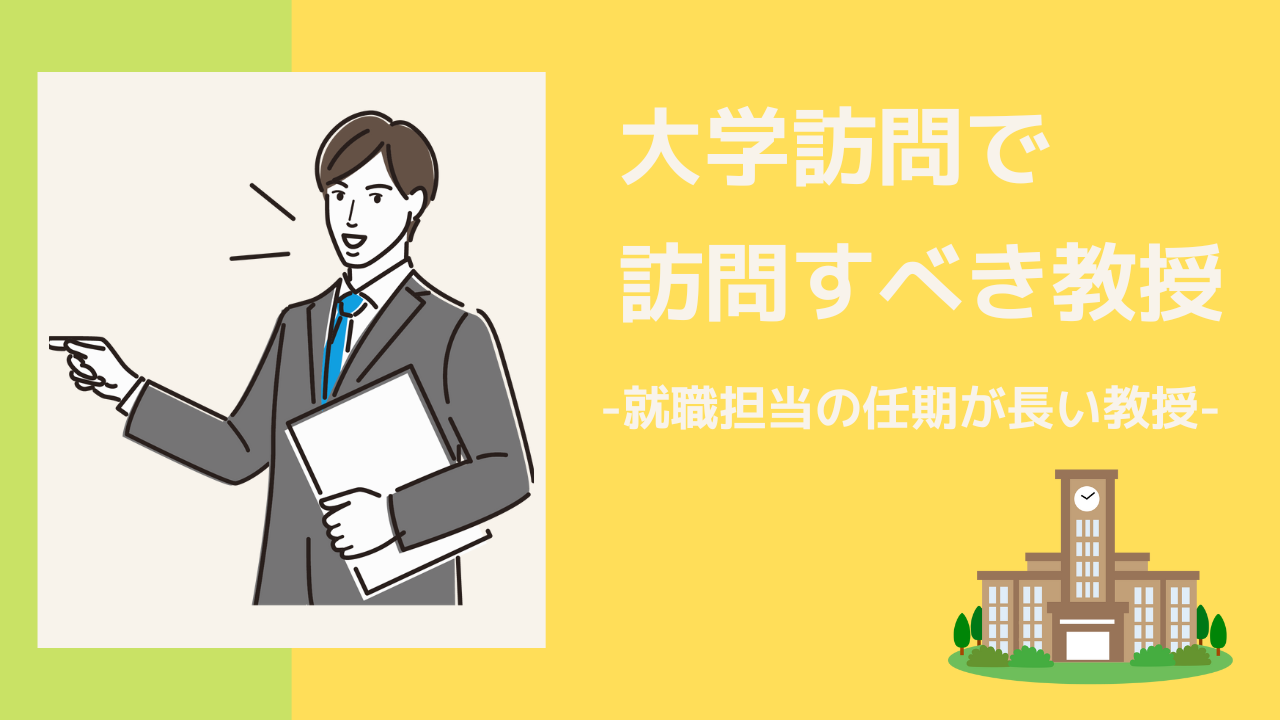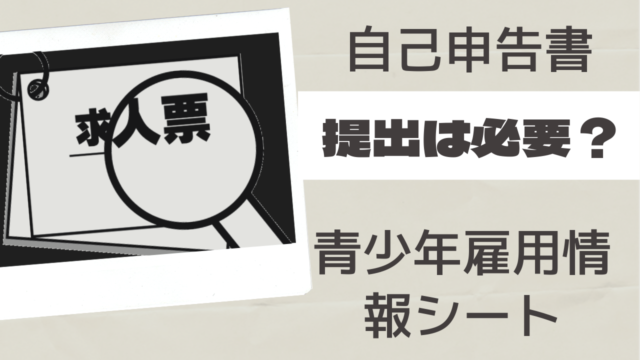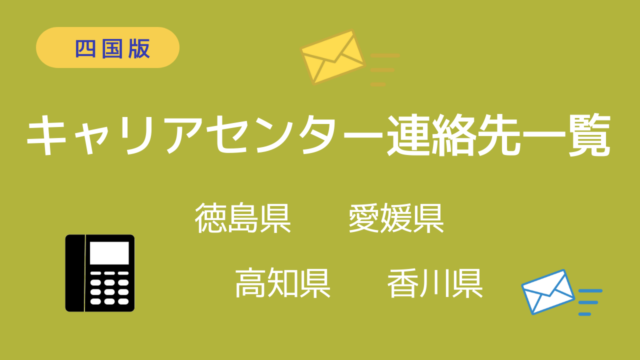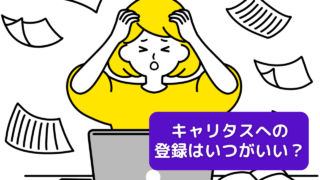各学科に存在する「就職幹事」
このサイト内でも何度かご紹介していますが、大学の各学科には「就職幹事(担当)」と言われる、その学科に所属している学生に対して推薦書を書いたり、就職支援を行う担当教員が存在しています(大学によっていないケースもありますが)。
就職幹事のいない大学についてはこちらの記事をご覧ください。
↓ ↓
大学訪問の行き先について質問された時には、求人票を提出する場合や、学内合同説明会への参画依頼など、基本的な採用情報の公開を依頼する場合や、大学全体に対しては行うような広報は、キャリアセンターを訪問してお願いをすればいいのですが、「学部や学科を限定した採用活動を」を行っている場合は、キャリアセンターだけでなく、各学科の「就職幹事」も訪問することもおススメしています。
今回の内容は、就職幹事の任期にスポットを当て、それぞれのタイプについてご紹介していきます。
各タイプの就職幹事をご理解頂き、積極的にアプローチした方が良いタイプなのか?それとも残念なタイプなのか?をご判断して今後の大学訪問に生かして頂けると幸いです。
※今回はどちらかというと、すでに大学訪問を経験されている方向けのテーマになりますので、「就職幹事」について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
↓ ↓
就職幹事が変わらない学科が存在する訳
就職幹事の任期は、大学や学科によって変わるものの、数年で役割が持ち回ってくるようになっているのが一般的です。
就職幹事の任期や交代時期について詳しく書いた記事はこちらです。
しかし、稀にやたらと長くこの「就職幹事」や「就職担当」に就いている教授がおり、5年はおろか、人によっては10年以上というケースがあります。
こういった教授(学科)は、なぜこのように長きに渡って就職幹事を務めているのでしょうか?
はっきりとした理由は分かりませんが(該当する先生数名に、実際に聞いてみたこともありますが、皆さん正確なところは分からないという回答でした)、状況を聞く限り、最初の任期が延長になったことが元々の原因になっているケースが多いようです。
例えば、本来は2年で交代する持ち回りが、何かのタイミングで「もう1期」となり、更にもう「1期」となってこのスパイラルが続いているケースや、何となく交代の声が掛からないのでそのまま継続している。。。など。
長く続いている先生にその原因を聞くと、大概こういったケースが多い印象を受けます。
そして、この就職幹事期間の延長が続くことで厄介になってくるのが、「良い就職幹事」と「悪い就職幹事」が他の学科よりも顕著に現れてくることです。
どういったことなのか具体的に紹介していきます。
就職市場に詳しく協力的
長く就職支援に携わっていると、当然企業からの訪問も多くなり、就職市場にも詳しくなってきます。
また、積極的に就職支援を行うことで、年度を跨いでの学生の状況など新卒マーケットに関しても把握出来てくるので、我々が訪問した際の質問にも的確に答えてくれ、学内説明会などの実施や採用情報の公開にも協力的です。
こういった先生は人の良い方が多いので、周囲からも「ぜひ次回も」とお願いされると断れずに引き受けて。。。そのスパイラルになっていることが多いです。
採用側からすれば非常に良い先生になるため、ずっと就職幹事をやって頂きたいの、まさかの交代になった際のダメージは大きいです、、、
何もせずに続けている
就職に興味がないにも関わらず、同じ先生が就職幹事をずっとやっている学科が稀にあります。
以前の記事を読んでいる方であれば、「就職幹事なんてやりたくないのになぜ?」と思われるかもしれませんが、こういった先生はそもそも「何もしていない」ので、就職幹事だろうが何だろうが関係ないのです。
基本的に周りの先生方も、就職幹事はやりたくないのでその先生が継続することを希望→本人は就職幹事の仕事をしていないので継続に支障もなく今回も任期継続。
こうなってくると、該当する学科は攻略するのが非常に難しくなってきますので、内定者など関係性のある研究室やゼミから攻めの糸口を見つけていくことになります。
やっていると思い込み型就職幹事
仕事をしない就職幹事も厄介なのですが、「自分でやっていると思い込んでいる」「就職幹事は自分しかいないと思い込んでいる」ケースもまた面倒で厄介なパターンです。
まず前者ですが、こちらは就職幹事として最低限の仕事しか出来ていないにも関わらず、自身では就職幹事としての任務はしっかりと遂行出来ていると思い込んでいるケース。
後者は、「学科内で自分が最も就職状況に熟知している」と思い込んでいるので、転職市場や学生の状況に詳しいこともありますが、周りから依頼されるよりも、「自分しかいない」と積極的に継続が続いているケース。
前者の就職幹事が行う業務は、企業から送られてきたメールをそのまま転送。持参した求人や企業の資料を資料室に置く、もしくは山積みにしておく。学生から聞かれたら答える(自分からは動かない)。この程度です。
元々たいした支援を行っていない学科(前任者)の内容をそのまま引き継ぎ、その部分だけしっかりと遂行しているため、やっていない訳ではないのですが発展性も何もないケース、協力的だった先生から引き継いだものの、最低限の業務に変えてしまうケースなどがあります。※先生に依存するなどと言われる由来はここにあります。
このケースが厄介なのは、「表面的には協力的に見える」ところです。
対応も良く(見える)、動いてくれる(ように見える)ので、大学訪問を始めたばかりの担当者にとっては、「協力的」に見えてしまうからです。
こう言った就職幹事の場合は、「それ以上に何かをしてもらう」ことは非常に難しいです(ほぼ無理)。
就職情報の偏りが強い
もう一方の「学科内で自分が最も就職状況に熟知している」と思い込んでいるケース。
こちらは先程も書いたように、新卒の就職市場や学生の状況に詳しいのですが、中途半端なことが多く、何よりも、「●●業界は良い」「●●業界は悪い」などと、自身の考え方が固まってしまっており、就職情報が全くアップデートされていない方が多い印象を受けます。
こういった方は、自分の情報のみが正義になっているので、就職幹事の長さに関わらず本当に厄介な就職幹事です。
厄介なケースが多い
ということで、「就職幹事」や「就職担当」が長いケースとその原因についてご紹介しましたが、結論を言えば、長く就職担当が変わらないのは、良いことよりも悪いことの方が多いですね。
これまで「就職幹事歴が長い」ということについて、真剣に考えたことはなかったですが、改めて考えてみると、全くコンタクトが取れていない(取ることが出来ない)ターゲットの学科は、長く就職幹事が変わっていないことが多いような気がします。
今後大学訪問を沢山行っていく予定の方、これから先いつまでも変わらない就職幹事に出会うことも多々あると思いますが、ぜひ心折れずに接して頂き、長く関係を続けていけることをお祈りしています。
そして、最初にご紹介した協力的な先生のような、「訪問すべき教授」を見つけて下さい。