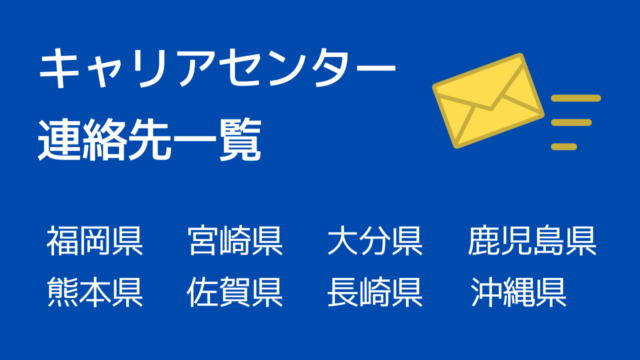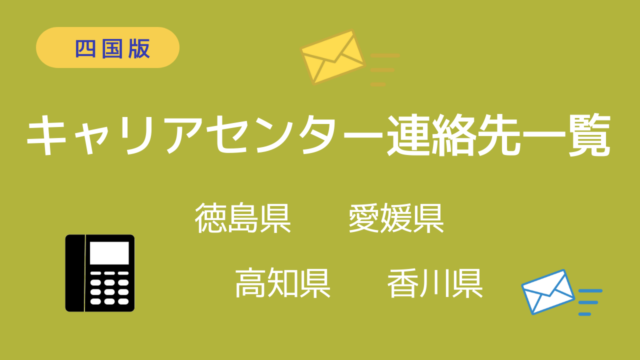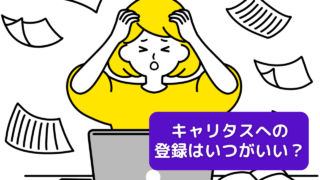活躍するリクルーター
採用難の時代になり、採用活動の中で再び「リクルーター」という存在が注目されはじめ、各社がこぞって採用活動にリクルーターを用いるようになってきてから、かれこれ10年以上が経ちます。
しかし、マイナビやリクナビなどの「就活サイト」なるものが登場するよりも遥か昔には、当たり前のように「リクルーター」という言葉は使われており、リクルーターを活用して採用活動は数多く行われてきました。
現在の採用活動において、リクルーターを積極的に活用しているという企業も増えてきたかと思いますが、通常の採用活動において活動するリクルーターと、大学訪問において活動するリクルーターは役割や適性が異なるので、もし同じ基準や観点で社内でリクルーターの選定をしているのであれば、少し注意して頂きたいと思います。
今回は、採用活動におけるリクルーターと、大学訪問におけるリクルーターの違いについてお伝えしていこうかと思っています。
これまで”同じ基準で考えていた”、という採用担当の方はぜひ一つの参考にして頂けると幸いです。
リクルーターってなに?
それぞれの違いについてお話する前に、まずは「そもそもリクルーターとは何ぞや?」という所からご紹介していきます。
「リクルーター」とは簡単に説明すると、採用活動の中で就活生に対して直接接触する、採用担当以外の現場で働く社員のことを差します。
そして、その存在が担う役割についてですが・・・
情報発信
リクルーターには、(企業にもよりますが)若手~ベテランまで幅広い世代の社員が登場します。
選考の過程で彼ら彼女らから語られる言葉には、採用担当が発信する情報(会社情報)とはまた違った、「仕事や職場の話」や「職場の雰囲気」といった情報発信をすることが出来ます。
※例えば、企業説明会で紹介されるキャリアステップの全体イメージに対して、リクルーターがそのペルソナとして情報提供を自身の体験談と共に語るなど。
志望度アップへ
就活生に対してリクルーターとの面談を実施している企業もあります。
新卒採用の場合、多くの学生が対象になり、中途に比べて軸が想像になりがちなため、発信する情報に強弱をつけるの(オリジナルの情報発信)が難しくなります。
そこで、「対象学生に似た属性」や「対象学生が目指す属性」のリクルーターとの面談を通じて、就活生個々の志望度の直接UPに繋げていきます。
情報収集
情報発信に対して、こちらは逆の「情報収集」です。
採用担当との「面接」ではなく、現場の先輩との「面談」を通すことで、学生は自己開示をし、面接では見せなかった一面を見せてくれることもあります。
面接では見えなかった長所や短所の発見、懸念材料の払拭や、新たな懸念材料が見えるなど、選考にプラスになる情報が集められる可能性もあります。
リクルーターは重要
ここまでいくつかご紹介しましたが、このようにリクルーターの存在は採用活動において非常に重要な役割を担っています。
だからこそ、その人選にはどの企業も細心の注意を払っており、それゆえに各社共リクルーターにはそれなりの「人材」の顔ぶれが並んでいることが多いのです。
大学訪問におけるリクルーターの選考基準
さて、前置きが随分と長くなりましたが、リクルーターの役割や重要性をご理解して頂いたところで、ここからは「大学訪問におけるリクルーター」についてお伝えします。
「同じリクルーターなんだから違いなんてあるの?」
そんな風に思う方も多くいると思いますが、「採用活動におけるリクルーター」と「大学訪問におけるリクルーター」では、適正や選考基準が若干異なってくると思います。
営業力
二つのリクルーター最大の相違点は、この営業力です。
採用活動の場合は「興味を持っているので、ぜひ話を聞きたいという学生」が伝える相手になるので、こちらの質問に対しても「丁寧な対応」をしてくれ、比較的こちらの「イメージに沿ったコミュニケーション」を取れることが多いです。
それに対いて大学訪問という場面では、「興味はないけど義理で話を聞く学生や先生」、場合によっては「全く話を聞く気がない・興味がない先生」が相手になるなど、用意していたプレゼンが通用しないケースも多々あります。
大学訪問を通して広報活動だけでなく、様々なルート発見や開拓をして欲しいので、学内において臨機応変に自社を広報活動してくれる営業力は重要なチェックポイントです。
大学との繋がり
採用強化したい大学のOBに、出身大学を訪問をしてもらうケースも多く見受けられますが、大学との繋がりは事前にチェックしておきましょう。
特に「研究室訪問」「ゼミ訪問」をさせる場合は、そのOBが研究室やゼミにおいてどのようなポジションだったのか?教授との関係性はどうだったのか?
その辺りはしっかりと確認することは必須です。
恐らく大丈夫かと思いますが、以前研究室と関係性が希薄だった学生を、大学訪問になぜか行かせたという例を聞いたことがあります。
学生との距離感
大学訪問をするリクルーター選定において時々見かけるミスが、「学生との距離感が近い」という部分を優先してしまうケースです。
採用活動において、説明会への協力や面談の実施などを行ってもらう先輩であれば「学生との距離感が近い」というパーソナリティーは重要なのですが、大学訪問の場合は先生や職員に対しても対応しなければいけないので、相手によって距離感を変化させる必要があります。
「学生目線での観点と社会人としての観点」です。
少し言い方を変えると、学生面談では「より詳細な職場での仕事や雰囲気」に対して、大学訪問では「業界や会社の規模や方向性」など枝ではなく幹に対しての質問が多いので、「学生気分での対応が是」と思ってしまうと足元をすくわれます。
大学訪問におけるリクルーター基準まとめ
ということで、今回は採用活動におけるリクルーターと、大学訪問におけるリクルーターの違いについてお伝えしました。
しかし、学生対応がしっかりと出来る方は、大学対応もしっかりと出来るケースが多いので、蓋を開けると顔ぶれがそれほど変わらないかもしれません(ここまで書いてきたのは何だったのかと言わないでください)。
以前も少しOB訪問の記事で触れましたが、社歴が長かったとしても採用活動という場面になると対応できる人は多くはなく、出来る人は勘所が良いのです。
とはいえ、やはり自社のテリトリー内で話をするのか?社外で対応するのか?それぞれ戦いの場が異なってきますので、リクルーターの人選の際には参考にして頂ければ幸いです。