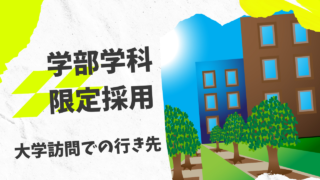Contents
オンライン学内合説は参加した方がいいのか??
毎年3月をメインに多くの大学が開催している「学内合同説明会」もまた、コロナの影響を受け、ここ数年はオンライン化が主流となりました。
「オンラインの学内合説は出た方がいいのか?」
「そもそもオンラインでの学内合説に参加して効果はあるのか?」
ここ数年「オンライン学内合説」についてよく聞かれる質問です。
いくつかのオンライン合説を経験したうえで結論から言えば、
「出ないより出た方が良いと思います。ただしリアルな学内合説よりも効果は低いと思います。」
いきなり結論から話をしてしまいましたが、これが個人的な意見になります。
オンライン学内合同説明会の実施方法
まずは効果云々の前に、現在各大学で実施されているオンライン合同説明会の実施方法について、簡単にまとめてみたいと思います。※ネーミングは勝手に付けていますので、正式な名称ではありません。
フルタイム実施型
まずは「フルタイム実施型」です。
こちらの実施方式は、●月●日 ●:●●~●:●●のイベントであれば、その時間内全てが自社の持ち時間になるという形式です。
発行されたURL、もしくは(Zoomであれば)ブレイクアウトされた部屋を、1つの企業が開催時間内ずっと使用出来る形式です。
URLをブースに見立てた場合、対面型の合同説明会がそのままオンライン会場に変わるイメージです。
全体の流れとしては、多くのケースが30分~40分を1タームとして、企業の部屋を学生が回っていくので、開催時間をタームの時間で割った回数分学生が着座?してくれるチャンスがあります。
午前中から夕方まで1日開催するケースもありますが、この形式で最も多いケースとしては(あくまで体感ですが)、1日を前半後半に分けて、1ターム30分(説明時間・質問時間などの時間配分は企業が決める)で、4回転くらいの合説が一番多い印象です。
時間分割型
オンライン学内合同説明会の実施方法として、フルタイム実施型と並んで多いのがこの「時間分割型」ではないでしょうか?
こちらの実施方法は簡単に言ってしまえば、フルタイム実施型の各ターム毎に企業を入れ替える方法です。そのため、フルタイム実施型に比べると学生との接触数は減ってしまいます。
ここまで読んで頂くと分かると思いますが、オンライン学内合説は、1日の実施時間を一つの企業が全て担当するか?複数の企業で担当するか?違いはそれだけです。
フルタイム実施型に午前午後で分けるケースがあるように、時間分割型も、1コマ1企業ずつで行う大学もあれば、1企業が2コマ担当する大学もあり内容は様々です。
学内オンライン合説の参加費用はいくら?
オンライン学内合説の参加費用ですが、その参加費用は無料の所から10万円以上と大学によってかなり変わってきます。
データを集めたわけではありませんが、対面で実施していた頃は無料で行っていた大学の方が多く、有料開催の方が珍しかった記憶がありますが(わずか2年前にも関わらず遠い昔のような記憶です)、オンライン実施がメインとなった現在は有料開催も増えてきています。
これもあくまで個人的な印象ですが、対面でこれまで無料で開催していた大学が有料になったケースはいくつかありましたが、その逆は殆んどなかったように思います。
オンラインであれば会場・設営費や、スタッフの人件費が発生しないためむしろ無料になりそうですが、、、
そんな意見を言う方もいらっしゃるかもしれませんが、大学の合説は外部の業者に丸投げしているケースも多いため、元々委託費や外注費が発生している大学もあるのです。
それをオンライン開催にしたとしても、人件費やシステム費用などは発生しているはずで、むしろ今回オンライン化に移行する業務を学内で行うノウハウや時間がなく、このタイミングで外注にしてしまったケースもあるのではないでしょうか?
大学としては、お客さんである学生へのサービスとして実施する学内合説になるので、費用を学生から取るわけにはいきません(既に頂いておりますし)。
そうなると、「無料で提供するか」「企業から費用を徴収するか」になるわけですが、中には「うちの大学の学生はレベルが高いのである程度の金額に設定してでも参加したい企業はるはず」という強気な価格設定をしている大学もあります(某大学OB会の方がおっしゃっていました)。
学内合説は対面式を選ぶべき
ここまでで、オンライン学内合同説明会の開催方法と費用についてご理解頂けたかと思います。
それでは最後に、冒頭でお答えした、「オンライン学内合説に出展した方がいいのか?」の回答、
「出ないより出た方が良いが、対面よりも効果は低い」その理由について述べていきたいと思います。
その理由はただ一つ、「本来の学内合同説明会の魅力を殆んど失っているからです」
多くの企業に一同に会える
学内合説に限らず、「合同企業説明会」と言われれば、多くの方が「複数の企業が1つの会場に集まり説明会を実施しているもの」を想像すると思います。
本来であれば複数会場の移動に費やす時間や、その際に掛かる費用が必要になったり、日程の関係で機会損失になってしまうマイナス面を解消できるのが、合同説明会でした。
実施会場に足を運ぶだけで、一気に複数の企業研究が出来てしまう。
しかし、今回のオンライン化で通常の説明会がオンラインとなり「これまでの合同説明会と同じ位置づけになってしまい」、むしろオンライン合説は「ただ簡易的な説明をする企業が集まる場」という存在になってしまいました。
そのため、複数企業の情報収集であれば、オンライン説明会に参加した方が、より効率的に濃い情報収集が出来るのです。
地方の大学でも直接触れることができる
こちらも同じような理由です。
企業の集まる都市部への移動時間や、交通費の問題を抱える地方大学の学生にとって、大学に複数の企業が足を運び直に話を聞ける学内合同説明会は意味がありました。
その証拠に、学内合説の広報活動を学内で積極的に行う大学も数年前までは多く存在しました。
しかし、こちらもオンライン化により本来のメリットは薄れてしまい、先程同様に「オンライン上で簡易的な説明をする企業が集まる場」という位置づけになってしまいました。
そんなイベントにわざわざ参加するのであれば、「オンライン説明会」に参加した方が、より詳しい内容を簡単に聞けるのです。
偶然の出会い
本命の会社の説明会をメインで聞きにきたものの、関がなく隣のブースで時間潰しのつもりが、、、、
こんな偶然の出会いもまた、合同説明会の良き風物詩でした。
特に学内合説の場合はOBOGが参加するので、意外に雑談が盛り上がり。。。なんていうこともあったのですが、これもオンライン化によって激減してしまったはずです。
そもそも会場という概念のないオンラインということもありますが、画面上でのコミュニケーションでは良い意味での「無駄な話」がしづらいので、ささいな話が発展することがあまりありません。
そして大学によっては、事前に学生から当日の予約受付を取るケースがあります。この場合は事前に参加者が分かるので、予約の入っていない企業は入室の必要さえなく、別の業務が行え、学生もまた必要な企業の話が終われば、退出して即座に別の場所や授業に出たりできます。
もはや偶然など存在するわけもなく、「合同」なのかさえ分からない状態です。
雰囲気もあったもんじゃない
直に企業の人が訪れるので、「企業の雰囲気に触れることが出来る」のも合同説明会の魅力でした。
しかし、オンラインでは先程のように雑談が盛り上がりにくく、そのために社風はおろか担当者の雰囲気さえ感じることが非常に難しくなってしまいました。
恐らく採用担当者も、オンライン説明会や選考を実施しているはずですので、これらの感覚は何となく共感して頂けるのではないでしょうか?
ハガキからリクナビに変わった時代
この状況を見て思うのが、就活がオンラインに移り変わった頃に似ているなということです。
かつて企業から情報を得るために一枚一枚ハガキを書き、エントリーシートも手書きの物を送っていた時代がありましたが、リクナビやマイナビの登場で「情報収集」と「エントリー」が容易になりました。
そして現在、その先にあった「参加」という部分までもが自宅で行えるようになりました。
良い悪いは別として、今回のコロナ騒動は間違いなく、就活や採用が新時代に向かうためのきっかけになる出来事になったのではないでしょうか?
3万円で3コマまで
最期に「オンライン学内合説の相場観」はどれくらいか?という問題。
これは企業やその担当者によって感覚値で変わってくると思いますが、あくまで個人的な意見として聞いて下さい。
オンライン学内合説は、「3コマ3万円」くらいまでが、参加を検討するギリギリのラインだと思います。
それ以上になると、効果を考えた時に高過ぎるのではないでしょうか?
そして、参加するのであれば、対面式の合同説明会同様に対策をしっかりと行い、準備して臨んで欲しいと思います。