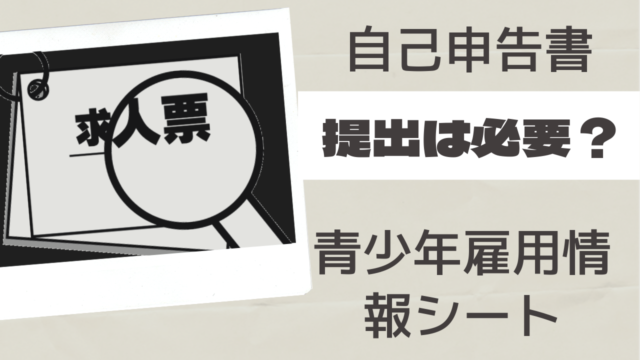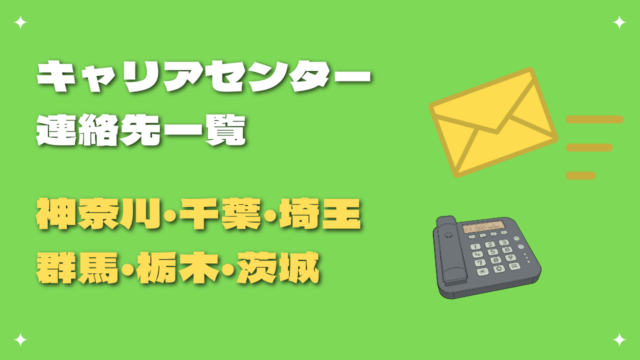大学訪問に行くことになったけど、そもそもキャリアセンターで何を話していいか分からない。
今回は「キャリアセンターを訪問した際、何を話せばいいのか?」ということを、細かくご紹介していきたいと思います。この記事を読んで頂ければ、明日キャリアセンターに行っても何の心配もありません。
会社について話す
キャリアセンターを訪問、名刺交換を行い、「校舎が綺麗ですね」のような世間話をしたら(笑)、まずは「会社について」の話題から話し始めましょう。
ほとんどの採用担当者は会社案内(パンフレット)を持参されていると思いますが、オススメしないのが、「会社案内を取り出してダラダラと説明するケース。この説明パターンは意外に多いのですが、止めた方がいいです。
キャリアセンターには日夜多くの会社から求人情報が届き、キャリアセンターの職員は各担当者から採用情報を耳にする機会も多いです。
そんな中、改めて対面で「弊社は〜」のように、会社案内などを使用してダラダラと詳細を説明されるのは苦痛です。何より区別がつきません。
会社案内ではなく求人票を見せましょう。会社の基本情報(設立、本社、従業員数など)はそこに記載しているはずなので、気になれば質問がくるはずです。
「会社について」の中で採用担当者が伝える最初のことは、「何を生業としている会社なのか?」です。
大学の職員の中でには「社会経験」がない人も多く在籍しているので、想像の世界で判断している方もいらっしゃいます。他社との違いを含め、誰にでもわかる簡単な説明をしましょう。就職市場に明るい職員の方であっても、これは同じです。
ちなみに誰でも知っている超大手企業の場合は、「世間が抱いている一番印象の強い事業」以外も行っていることを(恐らく多角的に行っていると思うので)アピールしてみるのも良いかもしれません。
「そんなこともやっているんですね」と言われるはずです。
OB・OG情報について話す
会社についてを理解して頂いたら、次はOBOG情報(採用実績)について紹介しましょう。
時々「新卒実績なのか?」にこだわる採用担当者がいますが、中途を含めても問題ありません。これまで大学訪問を行ってきた中で、この段階において大学側から「新卒か?中途か?」を聞かれたことや、そこを気にしている担当者に出会ったことはありませんでした。
こう行った背景もあるので、お伝えするのは新卒で該当する大学から入社した「採用実績」ではなく、あくまで「出身大学の在籍数」で構いません。
ちなみに新卒だけでも比較的多くの在籍人数がいる場合は、その旨を伝えて頂けると良いと思います。
また、「OBOGリストを準備した方が良いのか?」といった質問も頂きますが、どちらでも良いです。出身学科、個人名まで入ったものを持参したとしても、最近のキャリアセンターではそのリスト(個人情報)を受け取る可能性は低く、確認したところで何のメリットもありません。もしOBOGに関する情報を持参するのであれば、「出身が学部や学科が分かる程度」のリストで問題ないです。※研究室が関わるとリストの存在は、キャリアセンターとは異なりますが。。。
話がそれましたが、OBOGの在籍数を伝えたら、現在の活躍している状況をざっくりと話しましょう。キャリアセンターの職員が個人を特定し、活躍を喜ぶ可能性は限りなくゼロに等しいので、「活躍している情報」をメインに話つつ、伝える本当の意味は「在籍している長さ」や「辞めずに長く勤務している様子」です。
ちなみに大学訪問にOBOGを同行させるケースはよくありますが、キャリアセンターへの同行は正直それほどメリットはないと思います。
大学との繋がりについて話す
会社についてとOBOGについて伝えたら、次は「大学との繋がり」です。
「繋がり」と言っても共同研究などと言った難しい話ではなく、学内合説への参加実績・学内説明会の開催実績、過去の大学訪問の実績など、これまでの大学との繋がりです(学内で何かイベントを行っていたりすればそれも)。
大学には数多くの企業が訪問してきているので、出来るだけ大学との近さをアピールしたいところです。
もちろん、研究室やゼミの先生との繋がりがあれば、それも積極的にお伝え下さい。また、OBOG実績と被りますが、直近(ここ1.2年)での採用実績があればそれも伝えて下さい。
合説や説明会などの採用イベントに関しては、案外共有されていないケースも多いですのでしっかりと伝えて下さい。
採用状況について話す
大学との繋がりに関して話をしたら、いよいよ「求人情報」について話す番です。
ただしこちらも、求人内容についてダラダラ伝えるのではなく、求人情報に掲載されていない情報をお伝え下さい。
例えば、今年度選考に参加する学生の傾向や、こんなところに気を付けてほしいところ、募集人数が増えたのであればその理由、選考においてどこを見ているか?などです。
キャリアセンターの職員も、(基本的には)学生に対して情報発信をするので、見れば分かる企業情報よりも、「見えない裏情報」や「企業はこんなところをチェックしている」などという、学生にとってプラスになるような情報を求めているからです(自身の評価も上がります)。
特にコロナ禍になって以降、企業側の採用温度感や、選考の実施方法などもより多様になってきたので、その辺りを気にしている担当者も多い印象を受けます。
ここまで一気に書いてきましたが、各項目ごとしっかりと相手に質問をしながら進めて行って下さい。質問をしながら進め、必ず質問される項目に関しては、ツールの修正か伝え方を変えなければいけません。
ヒヤリングも忘れずに
大学訪問に行った時に何を話すか?何を伝えるのか?というのが、今回のテーマだったのですが、大学訪問で重要なことは「伝えること」ではなく、実は「情報を聞きだす」なのです。
「企業の採用情報を提供」→「興味のある学生に紹介」「学内合説に参加」というパターンが大学訪問の王道と、思っている方も多いと思いますが、大学訪問はあくまで営業になるので、商品(自社のこと)について話すことよりも、相手の状況について聞き出し、何かアクションを起こすことが重要なのです。※情報提供を目的としている企業も多くあるので、ここまで行う必要がないこともありますが。
例えば、大学側の状況を聞き出すことにより、自社が「採用対象になる学科」・「採用出来そうな学科」・「就職に強い(弱い)学科」など、学内の状況を把握することが出来、採用を強化する学部や学科が明確になれば、次回までのその学部や学科の出身者を探したり、これまで接点がなかったのか?などを調べることが出来るのです。
「キャリアセンターで何を話そう?何を持って行こう?」と悩む気持ちも分かりますが、聞くことも忘れないでください。あなたは大学の営業部隊なのです。
ちなみに気にする方が多い「大学訪問に手土産を持っていった方が良いのか?」ということですが、こちらは不要です。