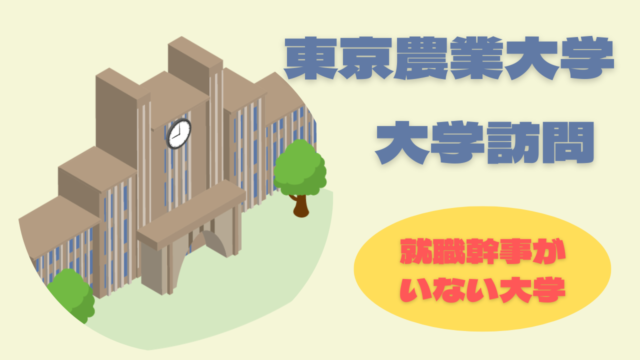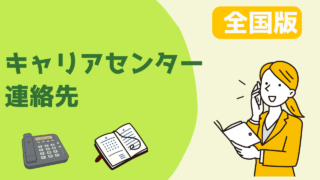どこの大学のキャリアセンターが一番良いか?
「どこの大学のキャリアセンターが一番良いか?」
「キャリアセンターが優秀なのはどこの大学か?」
大学訪問に関する質問としてよくされる一つです。
非常に難しいのが、「良いとは何が良いのか?」ということです(笑)
アポが取りやすいのか?対応が良いのか?就職状況を良く知っているのか?
人によって異なるのだと思いますが、私にとって良いキャリアセンターの定義というのはなく、代わり「良いキャリアセンターの職員」という定義を持って大学訪問をしています。
今回は、その辺りを少しご紹介出来ればと思っています。
キャリアセンターはどこも綺麗
まず、「なぜ私にとって良いキャリアセンターの定義というものがないのか?」という説明からしていきたいのですが、今の大学はキャリアセンターの機能についてだけ言えば、一部の大学を除けば「殆んどの大学のキャリアセンターがしっかりとしている」というのが現状だからです。
その中で「どこが良いか?」などという質問をされた所で、答えることは難しいのです。
それでは以下、一般的なキャリアセンターの機能を簡単にご紹介していきたいと思います。
求人システムの導入
前回の記事で、求人票の扱いについて書かせて頂いたように、現在は多くの大学が求人受付システムを導入するなどして、キャリアセンターに足を運ばない学生も含めた全学生に、平等に求人情報(企業情報)が行き届くような体制を整えています。
大学によっては求人情報だけでなく、説明会情報やインターンシップの情報などもメーリングリストや、在校生だけが閲覧できるシステムにUPすることで随時更新された情報を配信しています。
資料閲覧室の設置
キャリアセンターの横にパソコンや机が用意され、学生が自由に使用できるスペースを開放しているキャリアセンターも多くあります(全てではないです)。※大学によって呼称は異なりますが、「資料室」のような名前が多い印象です。
そこには企業から届いた情報が掲示してあったり、会社案内や求人票が保管されており、こちらも学生が自由に閲覧することが出来、場合によってはその情報を持ってキャリアセンターに相談することが出来ます。
非常に便利で良い空間だと思うのですが、最近はスマホを使って情報収集が簡単に出来てしまい、自身でパソコンを持っている学生も多くいるので、どこの大学もこの空間を使っている学生が少ない印象受け勿体ないなと感じています。
キャリアカウンセリング
資料室の使用頻度とは異なり、繁忙期になると学生の予約で埋まるのが、キャリアセンターへの「就職相談」です。
こちらは殆んどの大学が行っており、設定された時間枠に学生が予約をして就職相談を行うのですが、内容はその学生の就活進行状態によって様々です。
個人的な意見で言わせてもらうと、「全ての学生が平等に就職相談を大人に出来る」観点からも、キャリアセンターが行う就職支援の中で、最重要事項に匹敵することではないでしょうか?
企業対応
「企業からの採用情報を学生に配信(公開)する」ということであれば、全ての大学が行っていると思いますが、「企業の訪問に対しての対応」という観点になると、最近は大学毎によって対応が少し変わってきたような印象を受けます。
以前は「企業の生の声」を得るため、どこの大学もアポイントに対しては好意的に対応してくれることがほとんどでしたが、コロナを境に「オンライン」をメイン対応にして、実際に会うことをしなくなった大学も多くなったような気がします。
学生がオンラインに慣れて就活に効率化を求めるようになった今、キャリアセンターも合わせる必要があるのか?という点では疑問です。学生がオンラインや現場で得る情報と、キャリアセンターに企業持ち込んだり、キャリアセンターの職員にこぼす情報は異なります。
就活支援に回る大人たちまで学生に合わせてしまうと、キャリアセンター自体の必要性が無くなってしまうような気がします。
学内イベントの対応
学内では、複数の企業を招いた「学内合同説明会」や、特定の企業が学内で説明会を実施する「学内説明会」が定期的(大学によって)に開催されています。
キャリアセンターでは、その企画や運営を行っています。最近では大部分の業務を媒体会社に依頼している大学も多いので、キャリアセンターの役割がどこまでかは不明ですが、イベントの仕切りもキャリアセンターでは実施しています。
キャリアセンターは職員で変わる
このように、求人情報(企業情報)の取り扱いや配信、イベントの仕切り、学生対応など、キャリアセンターでは「就活支援における必要最低限の機能」は兼ね備えています。
だから「良いキャリアセンター」という質問をされても、正直すぐに浮かんでくる大学はなく、「悪いキャリアセンターはない」といった感じの回答になってしまうのです。
昔に比べれば、どの大学でもキャリアセンターの機能はしっかりしている。というのが実情なのです。
しかし、このキャリアセンターの機能ですが、情報化の進んだ現在の学生であれば、自分で出来てしまうことが殆んどなのです。
企業情報の収集や合説への参加、企業担当との接触などは積極的に動けば可能であり、最近ではキャリアカウンセリングをしてくれる企業や団体も沢山あります。
つまり、キャリアセンターが本当に機能するためには、キャリアセンターに所属している職員が、それらの情報を最大化してオリジナルで発信しなければいけないのです。
そんな背景もあって、私はキャリアセンターの職員を重要視しています。
多少小さなキャリアセンターであっても、内定率が少し低かったとしても、熱心な職員の方であれば、こちらからの学生へのアプローチや情報配信のやり方を一緒に考えてくれたり、学生目線でバイアスのない就職支援の見解を見せてくれるのです。
大学にも企業同様人事異動があるので、残念ながら熱心な方も、就職課(キャリアセンター)から異動してしまうこともありますが、こうした熱心な職員の方に出会った場合、在籍期間中は必ずその方宛に伺うようにしています。
ということで、私はキャリアセンターに優劣は付けていませんが、キャリアセンターの職員の方に対して「優劣」を付けさせて頂いています。
次回は、ではその「優劣の付け方」はどこでしているのか?をご紹介していきたいと思います。